はじめに
食糧と人類 飢餓を克服した大増産の文明史 文庫
ルース・ドフリース (著), 小川 敏子 (翻訳)

副題に「飢餓を克服した」とあるが、それはあくまで現時点での話。
明日には飢えないかもしれない。でも、二年後、三年後はわからない。人類と胃袋との絶え間ない苦闘の歴史を科学的な観点から描いた良書です。
いまの日本で食糧があたりまえにあることが、先人たちのあくなき探求と、幸運な偶然、そして絶妙なバランスの上に成り立っていることを教えてくれます。
この本によると、たゆまぬ努力の結果、一人あたりが得られるカロリーは(世界に平等に分配するとした場合)、増え続けているそうです。
以下では、いくつか気になったトピックを引用してみたいと思います。
農耕を始めて栄養不足になった?
まずはこちら。
新しく栽培するようになった穀類は種類が少なくデンプン質が多いので、木の実、種子、ベリー類、肉を主食にしていたころよりも栄養状態が悪くなった。現存する頭蓋骨、骨、歯を調べると、炭水化物の多い食生活は、狩猟採集していた祖先にくらべて虫歯が増え、鉄分が不足しがちになり、平均身長が低くなっている。
農業が本業となるような地域は、自然豊かです。季節ごとに栽培している作物以外の味覚があります。春の山菜などがその好例。そういった食べ物が「美味しいから」という面だけでなく、栄養面でも優れていたことを始めて知りました。
農業は規格化しなければ、稼ぐことはできません。いっぽうでこういった事実にふれると、本当に栄養豊かなものをつくるってどういうことなんだろう? と考えさせられます。
食卓の多様性は失われつつあります。食にうるさいといわれる日本人であってもです。今後、世界はすべてマクドナルド化してしまうのでしょうか。
わずかな国の情勢に左右されるリン
リンは生命に欠かせない成分だそうです。SF作家のアイザック・アシモフは「リンが尽きるまで生きものは増えていけるが、リンが尽きてしまえば、どんな力をもってしても頭打ちとなる」と述べたと言います。そんな重要な資源であるリンに関して、こういった記述があります。
リン鉱石を蓄えた奇異な地質は世界各地に散らばっており、ひと握りの国がその上に陣どっている。今日、人類の食糧供給はいやおうなく、そうした少数の国々の情勢に左右されるということだ。
少数の国々とは、モロッコそして西サハラだそうです。どっちもよく知らない……。世界地図を持ってこられても、どこにあるか指し示すことすらできません。これらの国々のリンが無くなったらどうなるんだろう。
世界情勢が不安定な現代で、わずかな国々に人類の命運が握られていると思うとぞっとします。
肉を食べるのは悪いこと?
お肉って美味しい。血圧が高くても、コレステロールが多くても、まだまだ肉が旨いと感じる40代後半の私。でも、こんなことが書いてあって、少し考えてしまいましいた。
牛が食べるタンパク質のうち、わたしたちの食卓にのぼるタンパク質はわずか五パーセント。(中略)鶏肉の場合、餌として鶏に食べさせた穀類のタンパク質の二五パーセントが食卓にのる計算だ。鶏卵の場合は三〇パーセント、牛乳は四〇パーセントとなる。
地球のことを考えたら牛より鶏を食べた方が良いのでしょうか……。さらに言うと、鶏でもなく野菜を食べるほうが、地球にとって優しいかも? でも欲望にはなかなか勝てません。
肥満こそが最大の敵
ええ、肥満ですとも。それが何か? いや本当はしゅっとした身体を手に入れたいんですよ。農業をやることを考えたらなおさらです。
一九七〇年代に入ると、もっと安く糖分が手に入るようになった。日本の科学者がデンプンから糖を分離して大量生産する方法を発明し、「いままでにない甘味料を製造するための行程」の特許を申請したのが、その始まりだ。
糖分の製造方法なんて、てっきり消費大国アメリカが編み出したのかと思っていましたが、まさかの日本の発明でびっくりしました。
ほぼ全世界で肥満が増え、昔ながらの栄養豊かな食材が消えていく現象は、食糧大増産の弊害以外のなにものでもない。現在、世界各地で飢餓に苦しむ人数は一日一〇億人を切っている。肥満は一〇億人を突破している。飢えに苦しむ人々の数は減るいっぽう、肥満は増えている。
そりゃあ、糖が増えれば肥満になりますよね。本能にはあらがえない。アスリートや毎日のようにジムに通ってケアしている人たちは敬服に値します。
さいごに
少し本筋から離れたトピックも取り上げましたが「食糧」に対する考えをめぐらせるきっかけになる良い本です。一度手に取ってみることをおすすめします。
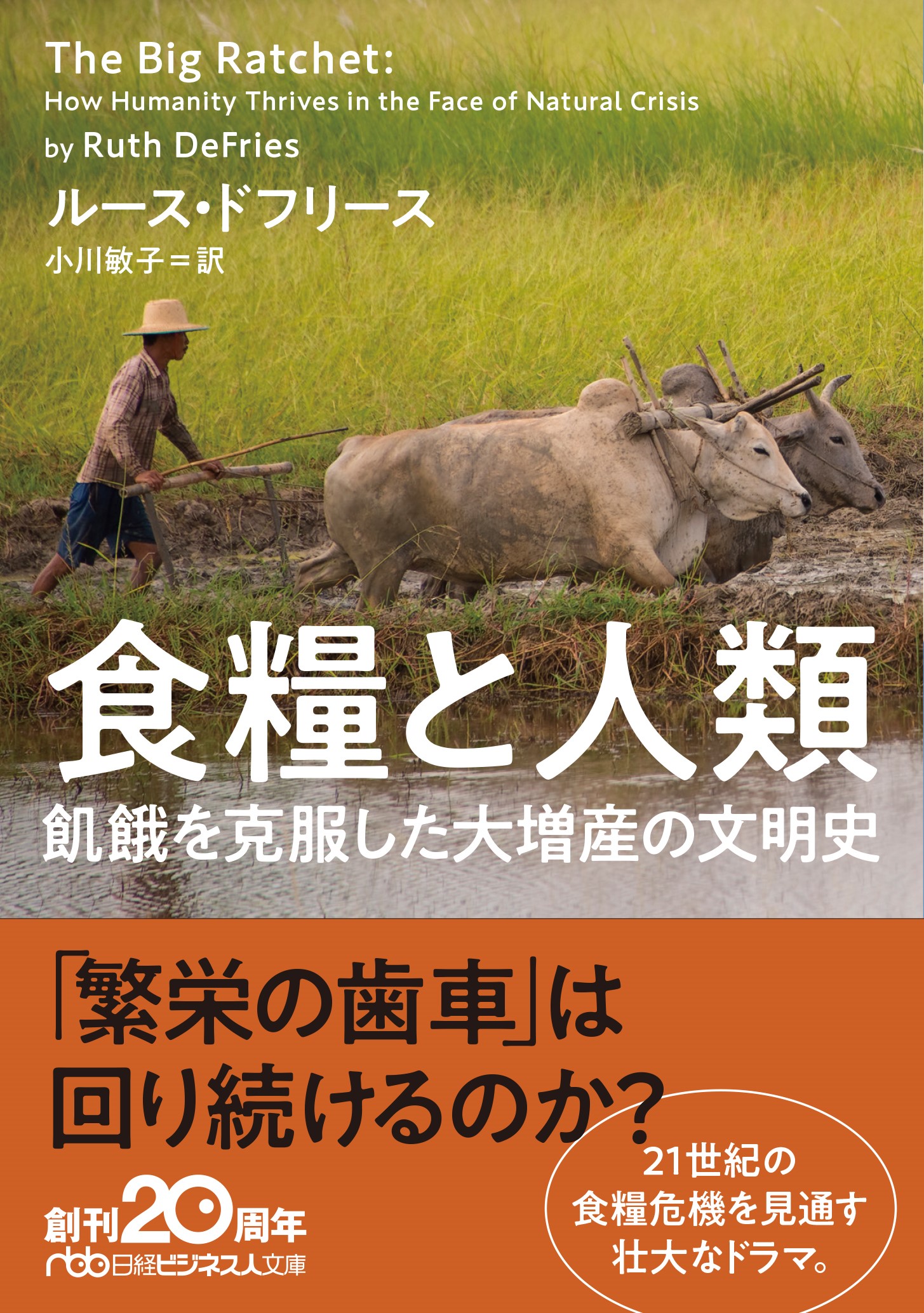
コメント