はじめに
「あ~、腹減ったな。冷蔵庫をあける。こんなものしかね~や。コンビニでも行くか」と言えること。これがどれだけ幸せなことか。
ロシアがウクライナに侵攻したとき「食糧危機になるかもしれない」という報道がありました。侵攻から二年。物価高騰は続いていますが、すくなくとも我が国は「危機」に陥っているという状況ではないように思います。
昨秋にはスーパーの店頭から米が無くなるという現象も起きました。これも一時的に騒がれたものの、現状では「買えない」という状況は解消されています。米をはじめ、諸々の物価はあがりましたが、日々の食糧を買えないということはありません。
私は氷河期世代と言われる世代ですが、就職が氷河期だっただけで「飢え」というものを知りません。いま日本で暮らしている多くの人が「飢え」におびえず生活できることは、本当に幸せなことです。
「飢え」とはどんなものか? そのことが気になり、この一冊を手に取りました。
飢饉は「三年に一度」
p.22 飢饉関係の編年史料として現在でも便利な西村真琴・吉川一郎編『日本凶荒史考』によれば、古代から江戸時代までに三七〇件ほどが目次として立項されている。約三年に一度の割合である。
平均寿命が短かったとはいえ、三年に一度となると一生のうちに何度も飢饉にみまわれることになります。飢饉に対する恐れ、そしてそれに対して考えを巡らす時間は今とは比較にならないでしょう。
飢饉は日本全土ということではなく、局所的におこる現象のようなので、一生飢饉と無縁だった人たちもいることでしょう。
しかしながら昨今増えたように思える水害や地震のように、人ごとではなく、身近にある危機だったととは言うまでもありません。現代ではそういった危機を身近に感じることはありません。そのことが、私たちを盲目にしてしまっているのではないでしょうか。
流通が飢饉を減らしてきた
p.41 近世型といってよい飢民の都市流入現象のはじまりは、大局的にみれば、農村と都市をつなぐ生産と流通が拡大してきたことが背景にあり、政治都市京都が富を集積し、飢饉時になっても持ちこたえられる経済力を蓄えてきたからだといえるだろう。
今日も荷物を届けてくれています。あまりに毎日のことすぎて感謝を忘れてしまいそうになります。
流通が飢饉を減らしてくれていたということは考えもしませんでした。
一方で、飢えると都市へ人が移動するという流れは、今も昔も変わらないような気がします。地方から都市への若者流出は続いています。それは食糧の「飢え」ではないかもしれませんが、多くは仕事の少なさや経済力の低さによるもののように思えます。
近世に入ってから続いてきたこの歴史を変えて地方の発展を求めるには、何か抜本的な改革が必要なのかもしれません。
マスメディアが果たした飢えに対する役割
p.48 マスメディアを通しての地域を越えた義捐金活動の役割も次第に大きくなっていく。この結果、日本の近代社会は江戸時代に比べ、はるかに飢饉に打たれ強くなったといえよう。
p.198 富める人は己の家内だけが生き残ればと考えず、人に施しをし、善を積むならば余慶があり子孫の栄えにもなる、と述べていた。
これは経済行為を肯定的にみながら、凶作・飢饉時の営利活動を戒めるものである。
現実には凶作・飢饉時に財をなして新興商人として力を蓄える者が出てくるのであるが、飢饉で儲けようというのは人倫にはずれる行為として指弾されていた。むしろ、人々が飢饉で苦しんでいる時には私財を投じて救済すべきものであった。
インターネットの登場、さらにはSNSの発展で、個人での情報発信が可能になりました。それでも、個人には限界があり、マスメディアは大きな役割を担っています。
しかしながら、マスメディアは市場経済にとらわれすぎ、本当の役割を忘れてしまっているようです。上記のような記述をみると近代から近世にかけてもマスメディアのほうが、よほど民のためになっており、気骨があるように感じます。
凶作の翌年のほうが大変
p.67 飢饉というのは凶作の翌年のほうが大変なのであって、凶作年の夏から翌夏までの一年間がおよそ飢饉状態にあった。人口の損失など地域社会のダメージが大きければ、それだけ復興にまた長期の年数がかかることになる。
昨秋の米不足がまさにこれでした。2023年の作付けの悪さが2024年の秋に影響したと言われています。こういっところは、物流や経済が高度に発展した現代でも対処が難しいようです。
食糧は何もないところからポンッと産み出すことはできません。どんなにカネがあっても産み出せません。時間が必要です。あまりに便利な世の中になったことで、そういった当然のことも私たちは忘れてしまったのかもしれません。
産業経済の原点とは
p.189 自給率の落ち込んだ農業だけでなく、産業の物づくりが列島社会で衰退しつつある。日本の産業技術を支えてきた職人的技術力が正当な扱いをされていない。物は外国で安く生産し、それを買って食べたり使えば効率がよいのだという、脳天気な自由貿易主義がこのところ横行してきた。
経済を発展させることは大切だと思います。そのためには「効率」を無視することはできません。カネを稼ぐ産業をつくる。金融や観光も大事なことでしょう。
しかし一方で、農業をはじめとして、人が生きるために必須な要素があまりにも軽んじられている気がしてなりません。
自国でまかなえるものをひとつでも増やしておくこと、増やそうという思想になっていくことを真剣に考えなければ、我々はいつまでも他国の為政者に首根っこをつかまれ押さえつけられているのです。そのような状態で自立した国になることなどできましょうか。
さいごに
この本のなかでは、飢饉の悲惨な実態(人肉食など)を史料をもとに紹介しています。それを読んで人ごとと考えるのでは無く、飢饉がおこってしまうメカニズムを知り、自ら何をできるか、そういったことを考えるきっかけになるかもしれません。
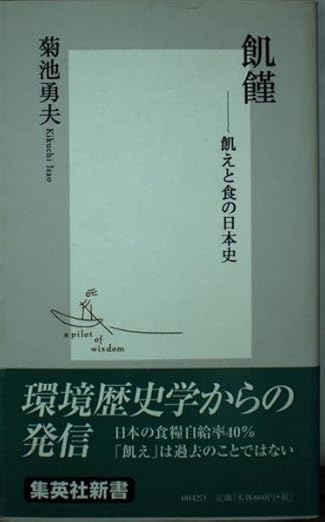
コメント